- HOME
- スカイ工法代理店とは?早わかりブログ
- 一人親方として独立・起業しよう!3つのメリットと、知っておきたい3つのリスクとは?
一人親方として独立・起業しよう!3つのメリットと、知っておきたい3つのリスクとは?

一人親方とは、建設業において労働者(従業員)を雇用せず、自分自身や家族のみで事業を行う個人事業主(※法人を設立せず、個人で事業を行う人のこと)のことです。一人親方として独立・起業することで、雇われている時より報酬が高くなる、自分のペースで仕事ができるなどのメリットがあります。その一方で、一人親方は個人事業主という働き方になることから、社会保障が受けられないなどのデメリットを伴うので注意しましょう。
本記事では、一人親方としての働き方を紹介し、一人親方として独立・起業するメリット・デメリットについて紹介します。
目次
一人親方に該当する方

画像引用:一人親方を守る法律!フリーランス保護新法は必ず知っておきましょう!(一人親方部会グループ)
一般的に「一人親方」に該当する方は、主に以下のとおりです。
- 労働者を使用しない、なおかつ会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
- 労働者を使用していても、使用期間が年間100日未満の見込みの方、および請負契約で仕事をしている方。
- 同居かつ同一生計の家族のみで、請負契約で仕事をしている方。
一人親方は、自分自身のみ、あるいは自分を含めた家族のみで業務を行います。一人親方のなかには、仕事が軌道に乗ってきたタイミングで、従業員を数人ほど雇う方も少なくありません。一人親方として新たに事業を開始する場合、管轄の税務署に開業届を提出し、手続きを行う必要があります。
開業届の作成・提出方法については「建設業で起業しよう!そんな時、開業届の提出は必要?開業届の概要、提出メリット、必要な準備・手続きについて徹底解説」で詳しく紹介していますので、開業の際には参考にしていただけると幸いです。
関連記事:建設業で一人親方として独立・起業する方法とは?独立するまでの6つのステップを紹介
一人親方として、独立・起業する3つのメリット
一人親方として独立・起業すると、さまざまなメリットを受けることができます。例えば以下の3点です
- 柔軟な働き方ができる
- 一人親方労災保険に特別加入できる
- 法人よりも、手続きが簡単である
メリット1. 柔軟な働き方ができる
 一人親方の場合、会社員として雇われている立場とは異なり、契約時に「単価」と「納期」を交渉することが可能です。技術力が高い、または単価交渉が上手な一人親方であれば、高い報酬を狙うこともできます。
一人親方の場合、会社員として雇われている立場とは異なり、契約時に「単価」と「納期」を交渉することが可能です。技術力が高い、または単価交渉が上手な一人親方であれば、高い報酬を狙うこともできます。
一人親方になると、取引先も自由に選べます。一人親方によっては、職人として雇われることもあれば、個人で取引先と請負契約を結ぶというケースもあります。そして一人親方は、自分の裁量で仕事量を調整することもできます。たとえば仕事を増やしたい時や稼ぎたい時はたくさん受注する、休みを取りたい時であれば仕事量を減らす、といった柔軟な働き方が可能です。
基本給が定まっている会社員と比べて、仕事を頑張れば頑張るほど稼げるのも、一人親方の魅力の一つと言えるでしょう。
メリット2. 一人親方労災保険に特別加入できる
個人事業主として働く場合、本来であれば労災保険には加入できません。ただし一人親方の場合、業務の実態が通常の労働者とほぼ変わらない、または怪我・事故のリスクが高いなどの理由から、労災保険に特別加入できます。労災保険に加入できるので、業務中に怪我・事故に遭遇した時も安心です。
一人親方労災保険にかかる費用は、労災保険料(※)、月500円の組合費、入会金1,000円のみ。その他、手数料は一切かかりません。一人親方労災保険は、年度途中での解約も可能です。
※労災保険料……労災保険料の金額は、給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円~25,000円までの16段階に応じて決定します。
参考記事:特別加入制度とは何ですか(厚生労働省)
参考記事:費用について(一人親方団体 労災センター共済会)
メリット3. 法人よりも、開業手続きが簡単である
法人会社を設立する時には、登記申請に必要な費用がかかります。個人事業主は、法人のように登記申請する必要がないので、費用をかけずに新規事業をスタートできます。
法人化の場合、会社設立の種類によって、申請にかかる費用が異なるので注意しましょう。設立にかかる費用は、以下のとおりです。
- 株式会社(株主と経営者が異なる人で構成されている)……25万円程度
- 合同会社(所有と経営が一致している場合)……10万円程度
株式会社を設立する時には、定款認証費用、登録免許税、別途資本金が必要です。合同会社は「定款の公証人の手数料」かからないため、株式会社より費用がかかりません。「将来的に法人化を検討しているが、費用をできる限り抑えたい」という場合は、合同会社を選択するのもひとつの手です。
その他にも、法人化をする場合は以下の書類が必要です。
- 設立登記申請書
- 定款
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人決定書(発起人が複数の場合は発起人会議事録)
- 代表取締役等の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 印鑑届書
- 出資金の払込証明書
個人事業主であれば、これらの書類を提出しなくて済むので、法人よりも手続きが簡単です。
参考記事:会社設立時に知っておくべき「株式会社」と「合同会社」の違いとメリット・デメリット(freee)
参考記事:会社登記(法人登記)とは?申請手順から変更までの基礎知識を解説(ビジドラ)
一人親方で独立・起業する3つのリスク
一人親方として独立・起業する際には、のちのち後悔しないためにも、リスク面も踏まえた上で決めることが大切です。ここでは、一人親方で独立・起業する3つのリスクについて紹介します。
- 社会的信用が低い
- 労力・金銭面の負担がある
- 雇用保険・健康保険(健保)・厚生年金に加入できない
リスク1. 社会的信用が低い
個人事業主は、法人よりも社会的信用が低くなります。企業によっては、信用度が低いなどの理由から、個人事業主との契約を避けるケースも少なくありません。そのため大きな企業と取引したい、取引先を増やしたいという場合であれば、法人を設立した方が良いでしょう。
さらに個人事業主は、原則として労働基準法の「労働者」とは認めらないため、労働基準法による保護を受けることはできません。労働基準法で保護されていない個人事業主は、取引する上で立場上弱くなりやすく、報酬の支払い遅延・未払いといったトラブルを受けるケースも少なくありません。不当な扱いを受けないためにも、取引先は慎重に選びましょう。
リスク2. 労力・金銭面の負担がある
一人親方は自分で仕事量を調整できる分、スケジュール管理能力が求められます。もちろん、たくさん稼ぎたい時は目一杯仕事を請け負うことも可能ですが、仕事を受けすぎて自身のキャパを超えてしまうと、納期に間に合わなくなり、取引先に迷惑をかけてしまう可能性も……。取引先に迷惑をかけないためにも、無理のない範囲で仕事を受注することが大切です。
さらに一人親方の場合、仕事に必要なもの。初期費用を1人で用意しなければなりません。一人親方として独立する際に、必要なもの・初期費用は以下のとおりです。
- 店舗費用、または事務所を借りるお金(保証金・前払い家賃・仲介手数料などが必要です。)
- 什器備品(筆記用具・事務用品・オフィス家具や備品など)
- 車両費(トラックなど)
- 運転資金(事業を行うのに必要な資金のこと)
開業資金は、事務所にかかる費用(部屋の広さ、場所によって賃貸料金・土地代が異なるため)、用意する車両・備品によって金額が異なります。建設業で開業した場合、事業を開始してから売上が入金されるまでに、3ヵ月ほどのタイムラグが発生するケースが多いため、運転資金は余裕をもって用意しておくと良いでしょう。
従業員を雇う場合は、「人数×3ヵ月分」の給料を用意しておくと安心
一人親方は、仕事が軌道に乗ってから従業員を雇うケースが多いです。ただし、なかには数人の従業員を事業開始直後から雇うというケースも少なくありません。最初から数人の従業員を雇う場合であれば、売上が入金されるより給料の支払いが先になる可能性が高いため、事前に「人数×3ヵ月分」の給料を事前に用意しておくと安心です。
参考記事:一人親方になるメリットとは?仕事をするうえで重要な3つのポイント(一人親方団体 労災センター共済会)
リスク3. 雇用保険・健康保険(健保)・厚生年金に加入できない
 個人事業主である一人親方は、雇用保険に加入できないので注意が必要です。雇用保険とは、失業時に失業給付、職業訓練が受けられる制度のことです。一人親方を辞めて働かなくなった場合、雇用保険に加入していないので失業給付・職業訓練を受けられないので注意しましょう。
個人事業主である一人親方は、雇用保険に加入できないので注意が必要です。雇用保険とは、失業時に失業給付、職業訓練が受けられる制度のことです。一人親方を辞めて働かなくなった場合、雇用保険に加入していないので失業給付・職業訓練を受けられないので注意しましょう。
さらに1人親方の場合、健康保険(健保)・厚生年金に加入できません。一人親方が加入できる国民健康保険(国保)は保険料が高い上に、国民年金の受給金額は厚生年金と比べて低くなります。一人親方として独立・起業する際には、雇用保険・健康保険(健保)・厚生年金に入れないという点についても、覚悟しておく必要があると言えそうです。
参考記事:一人親方は雇用保険に加入できるのか?(一人親方建設業共済会)
まとめ
一人親方として独立・起業するメリット、デメリットはそれぞれ以下のとおりです。
メリット
- 柔軟な働き方ができる
- 一人親方労災保険に特別加入できる
- 法人よりも、手続きが簡単である
リスク
- スケジュール管理ができない場合、取引先に迷惑がかかる
- 必要なもの・初期費用を、1人で用意しなければならない
- 雇用保険・健康保険(健保)・厚生年金に加入できない
.一人親方として起業する場合、初期費用(什器備品、事業を行うのに必要な運転資金など)などを1人で用意しなければなりません。「初期費用を抑えて、新規事業をスタートしたい」という方には、弊社のスカイ工法代理店制度を始めるのもひとつの手です。スカイ工法代理店であれば、施工に必要なものは、カッター・電動ノコギリ・はさみ・コーキンググッズのみ。
 初期設備はほぼかからないので、初期費用をかけずに新規事業を始めることが可能です。ご興味を持っていただいている方は、ぜひ弊社の「スカイ工法代理店制度」の加盟をご検討していただけると幸いです。
初期設備はほぼかからないので、初期費用をかけずに新規事業を始めることが可能です。ご興味を持っていただいている方は、ぜひ弊社の「スカイ工法代理店制度」の加盟をご検討していただけると幸いです。
営業として、日々さまざまな会社にサーモバリアの遮熱効果や施工事例をご紹介しております。セミナーを通じて、参加者の皆様にサーモバリアの良さを知っていただき、また「実演」で見ていただき、社会から必要とされる背景なども詳しくお伝えできればと思います。
関連記事
-
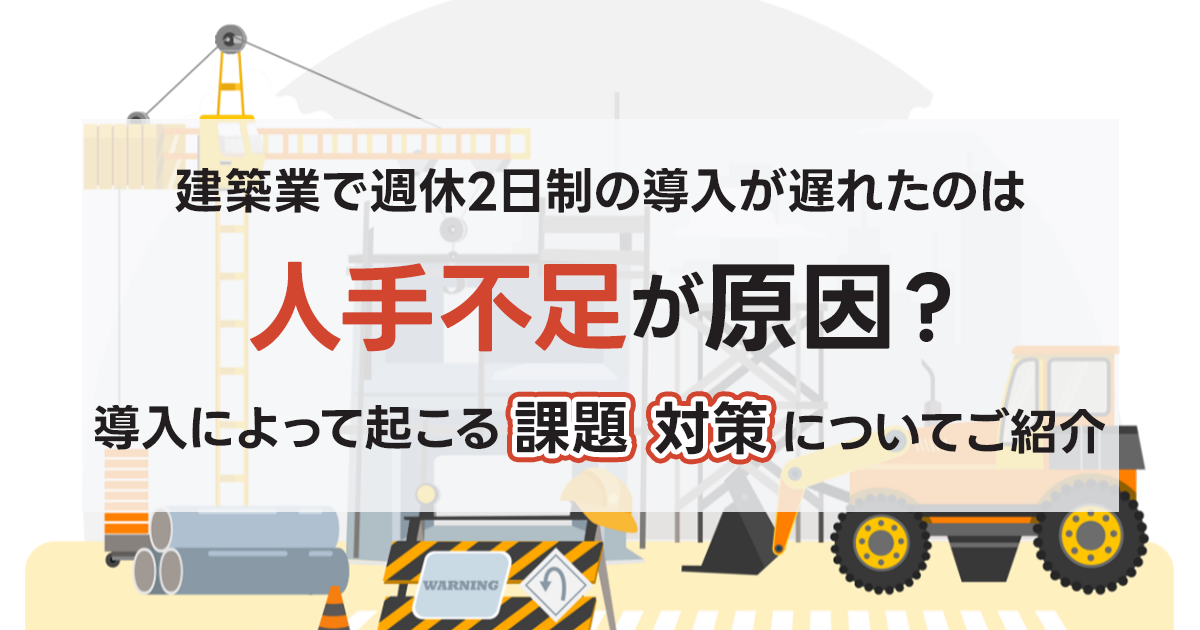 詳しく見る
詳しく見る建設業で週休2日制の導入が遅れたのは、人手不足が原因?導入によって起こる課題、対策について紹介
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業が人手不足で悩まされる理由とは?人手不足が起こる理由、対策を詳しく解説
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業の2024年問題とは?
桜井 宏樹 -
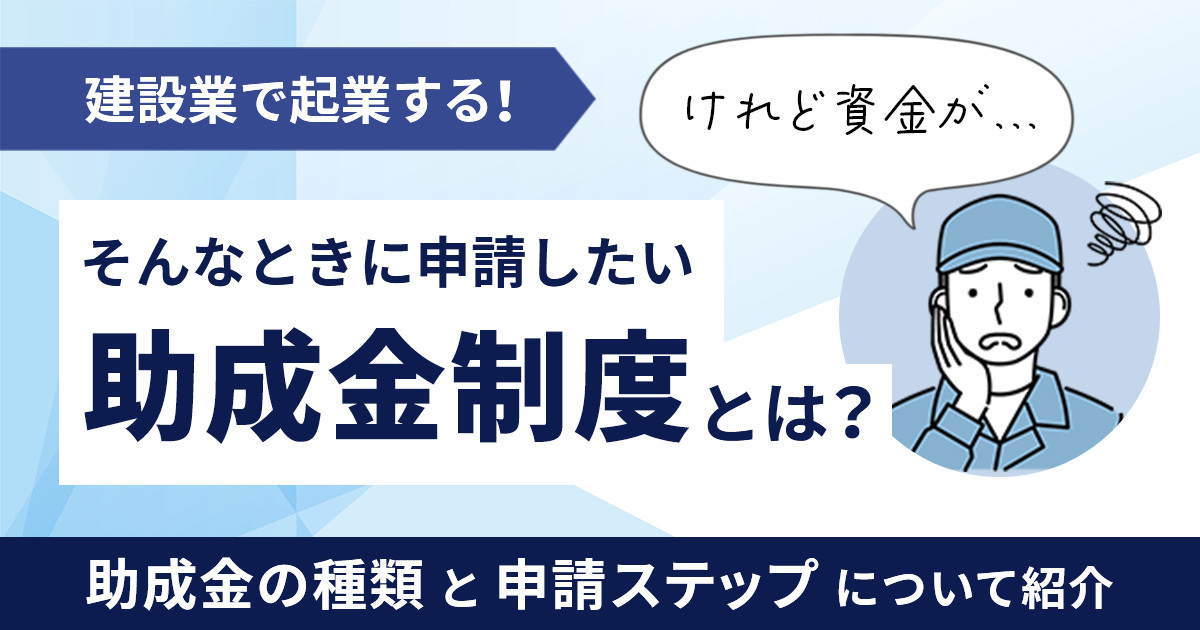 詳しく見る
詳しく見る「建設業で起業する!けれど資金が…」そんなときに申請したい助成金制度とは?助成金の種類と申請ステップについて紹介
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る一人親方は建設業許可票を取得した方が良い?取得するメリット、申請~取得までの5ステップを紹介
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業で起業しよう!起業の方法・必要な準備。そしてサーモバリアスカイ工法の代理店制度についてご紹介
桜井 宏樹 -
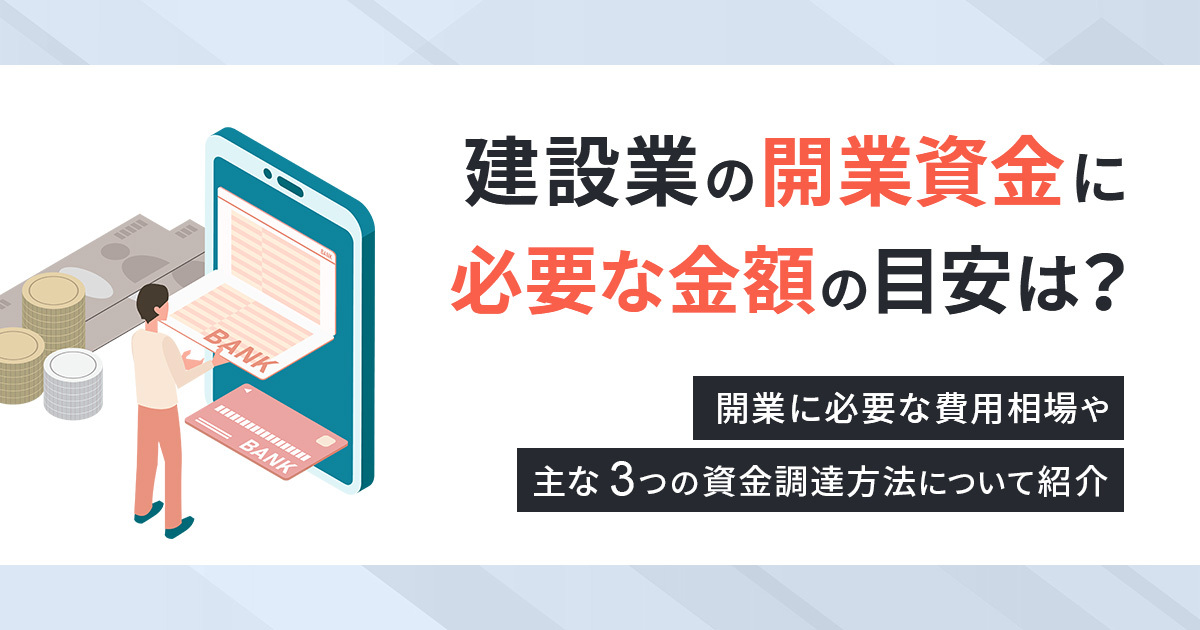 詳しく見る
詳しく見る建設業の開業資金に必要な金額の目安は?開業に必要な費用相場や、主な3つの資金調達方法について紹介
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業で一人親方として独立・起業する方法とは?独立するまでの6つのステップを紹介
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業で起業しよう!そんな時、開業届の提出は必要?開業届の概要、提出メリット、必要な準備・手続きについて徹底解説
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見るフランチャイズとは?フランチャイズを利用するメリット、加盟までの3つのステップをご紹介
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業で「独立開業」する方法とは?独立開業の方法、必要な準備・手続きについて紹介
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業許可票(金看板)とは?保有するメリットから取得までのステップについて詳しく解説。
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業の特許工法とは?特許工法の販売・施工を行う3つのメリットと、弊社の保有する特許工法について
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見るスカイ工法代理店加盟の隠れたメリット!?代理店一覧ページとインタビューへの掲載で得られる3つの効果
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る環境改善と企業イメージ向上にも貢献!サーモバリアスカイ工法が「SDGsの取り組み」にもつながるワケ
桜井 宏樹 -
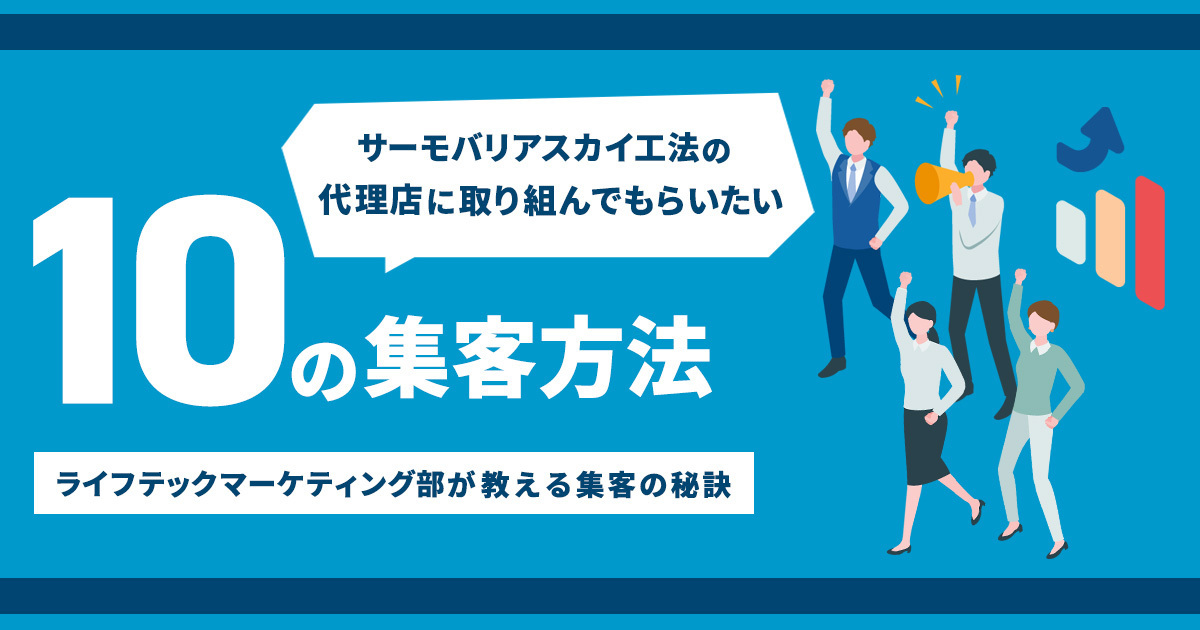 詳しく見る
詳しく見るサーモバリアスカイ工法の代理店に取り組んでもらいたい10の集客方法。ライフテックマーケティング部が教える集客の秘訣
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見るサーモバリア代理店が使用できる「営業キット」とは?営業キットに入っている6つのマル秘アイテムを公開!
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る「サーモバリアスカイ工法 代理店加盟説明会」では、どんな話を聞けるんだろう?説明会でお話ししている内容の一部を、少しだけ公開します。
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見るお問い合わせから代理店加盟までの「6ステップ」を解説!最短どれくらいで営業を始められるの?複雑な契約をしないといけない?といった不安にお答えします。
桜井 宏樹 -
詳しく見る
スカイ工法代理店のリアルな実態を7つに分けて公開します。
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る未経験でも安心!代理店の方々の施工・営業を手助けする研修「施工研修」と「営業研修」について。
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る初期費用を抑えて新規事業をスタートしよう。スカイ工法代理店制度が「加盟金0円」に設定している、たった1つの理由。
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見るスカイ工法だからこそ出来る!「初期費用0円」で新規事業を立ち上げれる理由って!?
桜井 宏樹 -
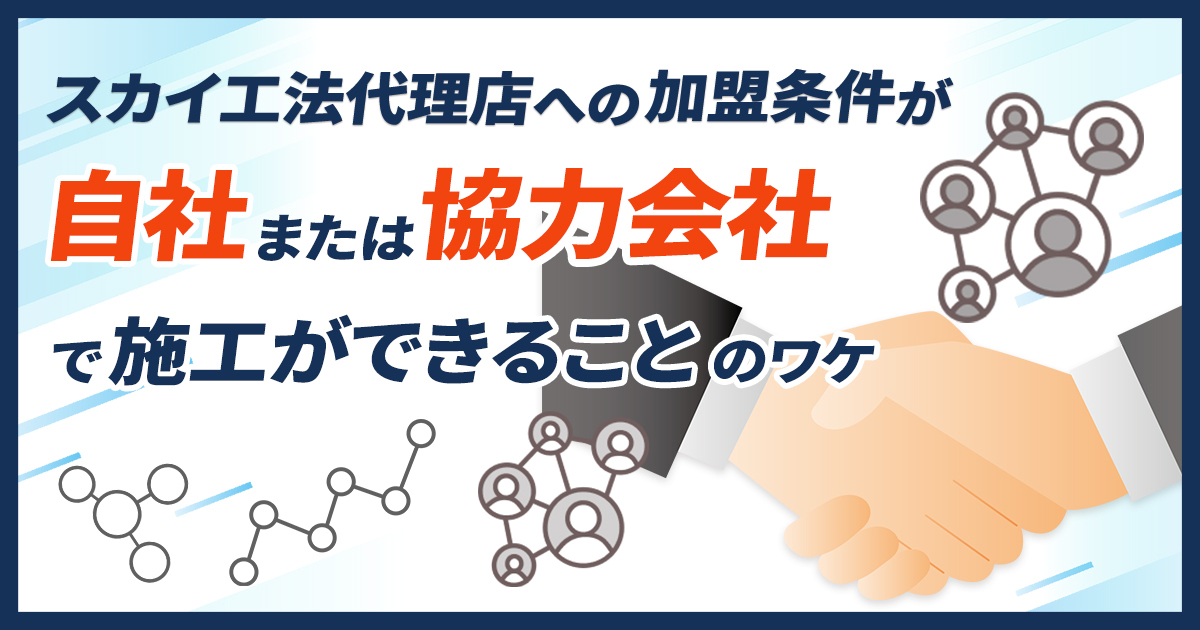 詳しく見る
詳しく見るスカイ工法代理店への加盟条件が「自社または協力会社で施工ができること」のワケ。
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見るスカイ工法代理店だけの特権!?特許工法「サーモバリア スカイ工法」とは?
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る「保証金」は何のための費用?スカイ工法代理店の加盟条件に「50万円以上の保証金が必要」としている理由
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見るスカイ工法代理店加盟条件に「窓口となる専任の担当者を必ず1名設置する」を設けている理由って?
桜井 宏樹 -
 詳しく見る
詳しく見る建設業許可票は絶対に必要?サーモバリア スカイ工法代理店になる上で「建設業許可票を保有していること」を必須としている理由
桜井 宏樹
